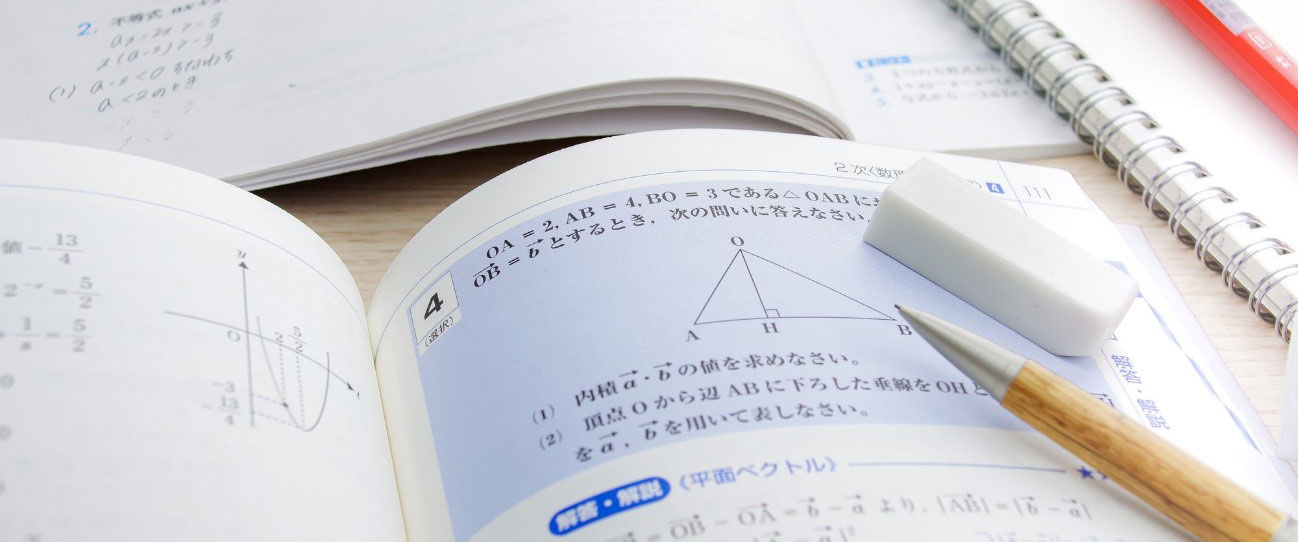
- 高校受験
算数と数学は何が違う?つまずきがちな子どもの特徴と克服のコツ
「算数は好きだったのに、数学になったら難しくなった気がする…」
そんなふうに感じている中高生や、「なぜ急につまずくのだろう?」と不安を抱える保護者の方も多いのではないでしょうか。
実は、算数と数学には「学ぶ目的」や「考え方」に大きな違いがあります。内容が変わるだけでなく、求められる力もガラリと変化するため、これまでと同じやり方では通用しないこともあるのです。
この記事では、算数と数学の違いをわかりやすく整理し、スムーズに学習を進めるためのポイントや、数学の苦手を克服するコツを紹介します。お子さんは自身はもちろん、保護者の方もぜひ一緒にチェックしてみてください。
本記事の目次

算数と数学の違いは?
「算数と数学って、同じように見えるけど何が違うの?」と感じる方もいるかもしれません。どちらも数字を扱う教科ですが、実は学ぶ目的や考え方には違いがあります。ここでは、定義・学習内容・難易度の3つの視点から、算数と数学の特徴を整理していきます。
学問の定義
算数は、日常生活に必要な計算や数量の考え方を学ぶ学問で、具体的な数字を扱う点が特徴です。「いくつ増える?」「いくらになる?」といった、生活に密着した問題を解くことが中心となります。
一方の数学は、抽象的な概念や論理的な思考を重視する学問です。文字や記号を用いて数理的に物事を考え、「なぜそうなるのか?」という過程を深く掘り下げながら問題に向き合っていきます。
学習内容
算数では、四則演算(たし算、ひき算、かけ算、わり算を使った基本となる計算方法)を中心に、分数・小数・グラフや図形の読み取りといった、身近な題材が学習の中心です。
一方、数学の学習では文字式や方程式、関数、証明など、抽象的な思考を必要とする内容が増えてきます。また、単元を超えた応用や、思考力・推論力が求められる場面も多くなっていきます。
学習難易度
算数は、具体的な数や図形を使って視覚的・直感的に解ける問題が多く、比較的取り組みやすい教科といえます。
それに対して数学では、「正解」だけではなく、「どうやってそこにたどり着いたか」というプロセスも評価の対象になります。複数の解法が存在する場合もあり、公式や定理を活用しながら思考を深める必要があるため、難しく感じることがあるのです。
算数と数学の「学ぶ目的」
学ぶ内容だけでなく、「なぜ学ぶのか」という目的も、算数と数学では異なります。ここでは、それぞれの教科が子どもたちのどんな力を育てているのかを見ていきましょう。
算数…日常生活で使う計算の仕方を学ぶ
算数では日常生活でも必要となる計算方法を学び、正しい答えを出せるようにすることが目的です。
具体的には、「ノートを買うのに500円玉を出したら、おつりはいくらになるか」といった四則計算に加えて、「分速80mで1時間歩けばどれくらい進めるか」といった時間や距離の計算方法、図形の面積や立体の体積を求める計算方法などを学びます。また、簡単な表やグラフの見方や作り方、平均値の求め方なども算数の範囲になっています。
日常生活でデータや数値を読み取り、正しく理解できるように基礎となる知識を学びます。
数学…算数で学んだことを土台とした論理的な思考を学ぶ
数学は、算数で学んできた知識を土台として、学んでいきます。XやYといった目に見えない抽象的な概念も登場し、それらを用いて「なぜそのような結果になるのか」を理解し、答えを出すまでの過程を論理的にあらわすことが重要になります。
具体的には、中学1年生では、正と負の数を理解し、それを含んだ四則計算、文字を用いた式の作り方や計算法、一元一次方程式、比例・反比例などが範囲です。中学2年生になると連立方程式や一次関数、中学3年生になると平方根、二次方程式、三平方の定理などを学びます。
また、「データの活用」の学習は、データを分類・整理したり、別の表形式にまとめたりして、表やグラフから何がいえるのかを読み取る能力を養うのが目的です。
\生徒ひとりひとりに合った指導で志望校合格へ導く/
算数から数学へ移る際につまずきがちな子どもの特徴
小学校の算数ではスムーズに進んでいたのに、中学校に入った途端に数学につまずく子どもが増えるのはなぜでしょうか。その理由は、算数と数学の違いに対応しきれず、基礎が不十分なまま応用に進んでしまうことにあります。ここでは、特に見られるつまずきのパターンを紹介します。
計算力が身についていない
算数で学ぶ基礎的な計算力(分数、小数、四則計算など)が十分でない場合、中学校で扱う複雑な計算や文字式の処理に苦労することがあります。特に、負の数や文字式のように抽象的な概念に入ると、計算の基本ができていない場合はミスを連発しがちです。
実際、数学ではひとつのミスが大きく響き、正しい考え方をしていても答えにたどり着けなくなります。複雑な式を正確に処理するためには、四則計算や分数・小数の計算といった「土台」がしっかりしていることが不可欠です。
公式を覚えていない
数学では、単なる暗記だけでは正解にたどり着けない問題が多くなりますが、それでも最低限覚えておかなければならない公式は存在します。たとえば、面積や体積、二次方程式や因数分解など、公式が頭に入っていないと解けない問題も少なくありません。
覚えるべき公式は、ただ暗記するのではなく、実際の問題の中で何度も使って体に染み込ませていくことが大切です。「覚えているつもり」が実はあやふやだったというケースも多いため、定期的に復習して確認することをおすすめします。
読解力が不足している
算数から数学になると、文章題はますます複雑になります。必要な情報を正確に読み取って、それを式に落とし込む力が求められます。しかし、読解力が不足していると、何を問われているのか理解できなかったり、関係のない数値に惑わされたりしてしまいます。
「国語が苦手な子は数学の文章題でも苦労する」と言われるのは、まさにこのためです。数学の文章題では、論理的に読み解く力も必要になるため、普段から文章を正確に読み、要点を整理する練習をしておくとよいでしょう。
わからないことを放置している
数学は、知識を積み重ねながら進んでいく教科です。一度つまずいた内容をそのままにしてしまうと、その後に出てくる関連分野の理解にも支障が出てしまいます。特に数学は前提知識をもとに新しい単元が成り立つため、「ちょっと苦手かも」と感じた段階での対処が必要です。
授業はどんどん進んでいくため、わからないことをそのままにしておくと、あっという間に取り残されてしまうかもしれません。理解できなかった部分があれば、すぐに先生や塾の講師に質問したり、自宅でしっかり復習したりして、早めにクリアにするよう心がけましょう。ひとつひとつを丁寧に理解していくことが、成績アップへの近道です。
数学の苦手を克服するコツ
数学が苦手と感じる原因は人それぞれです。まずは、どこでつまずいているのかを明らかにすることが、克服の第一歩になります。
基礎に立ち返る
苦手分野を発見したら、まずはその単元の基本から見直してみましょう。教科書の例題や、簡単な問題集から取り組むことで、理解がぐっと深まります。
特に公式や定理については、暗記するだけでなく「どんな場面で、なぜ使えるのか」といった意味まで理解しておくと、応用力も伸びていきます。
繰り返し問題を解く
「一度解けたから大丈夫」と思っても、定着していないことはよくあります。似た問題を繰り返し解くことで、知識がしっかりと自分のものになっていきます。さまざまな出題パターンに触れることで、対応力が養われ、テスト本番でも慌てずに解けるようになるでしょう。
途中式を書き残す
計算過程を省略してしまうと、ミスがあった場合にどこで間違えたのかがわからなくなってしまいます。途中式を丁寧に書くことで、自分の考えを整理しやすくなり、ケアレスミスも減っていきます。また、先生に質問するときも説明しやすくなるので、学習の効率も上がります。
信頼できる人に相談する
苦手を自力で克服するのは、時に大きな負担になります。そんなときは、学校の先生や塾の講師など、信頼できる人に相談してみましょう。専門的なアドバイスを受けることで、学習の方向性が見えてきます。
特にひとりひとりに寄り添った指導をしてくれる塾なら、つまずきに合わせたフォローが受けられるため、効果的に弱点を克服しやすくなります。
算数と数学の違いを踏まえて、意欲が高まる学習方法で定着率をアップさせよう
算数と数学は似ているようで大きな違いがあります。算数は計算力や基本的な公式の理解が中心ですが、数学では「なぜその答えになるのか」を考える論理的思考が求められます。小学生の頃の勉強法では思うように点数が伸びないこともあるため、数学に適した学習方法を取り入れることが大切です。学習に悩んだら、塾を活用するのもひとつの方法です。
そんな中でおすすめしたいのが「京進の中学・高校受験TOP∑」です。京進では、数学をはじめ、どの科目でも活用できる「目標設定」や「自主的な学習計画の立案」をサポート。着実に成績アップを目指せる環境が整っています。それでは、京進の学習方法がどのように役立つか、具体的に見ていきましょう。
目標を達成させる学習メソッド
京進では、脳科学に基づいた学習法を採用しています。まずは「ドリームツリー」を用いて、学習の目標を明確に設定。そのうえで、日々の学習計画を「学習ダイアリー」に記録することで、自主的な学びの習慣を身につけていきます。
目標があることで意欲も高まり、自然と学習に前向きになれる仕組みです。
「褒める指導」を行っている
京進では、小さな努力や成果にもきちんと目を向ける「褒める指導」を重視しています。できたことを認め、前向きな気持ちを育むことで、自信を持って学習に取り組めるようになります。
間違いを恐れず挑戦できる環境が整っているため、苦手意識を払拭することにもつながります。
AI学習ツールの「atama+」を採用している
京進の中学・高校受験TOP∑の数学の授業で採用している、AIを活用した学習ツール「atama+」は、個々の理解度に応じて適切な問題を提示してくれるシステムです。必要に応じて過去の単元にさかのぼって復習できる「さかのぼり学習」が可能なため、苦手な部分を確実に克服できます。
できる問題を増やす仕組みがある
定期的に実施される「週実テスト」や「まとめの週」での演習によって、できる問題を着実に増やしていけるのが京進の強みです。「循環発展学習法」に基づいたテストサイクルにより、理解度の定着と応用力の養成を両立させる学習が実現します。
算数と数学は一見似ていますが、その本質は大きく異なります。京進の中学・高校受験TOP∑では、そうした違いをふまえたうえで、個々の目標や学習スタイルに合わせたサポートを行っています。数学に限らず、勉強方法や成績アップでお悩みの方は、ぜひ一度ご相談ください。
お子さんが自信を持って学びを進められるよう、全力でサポートいたします。











